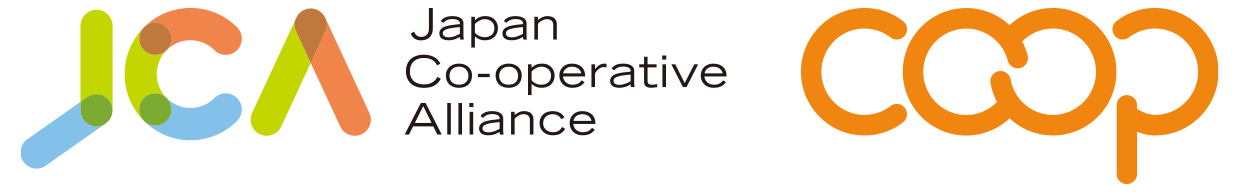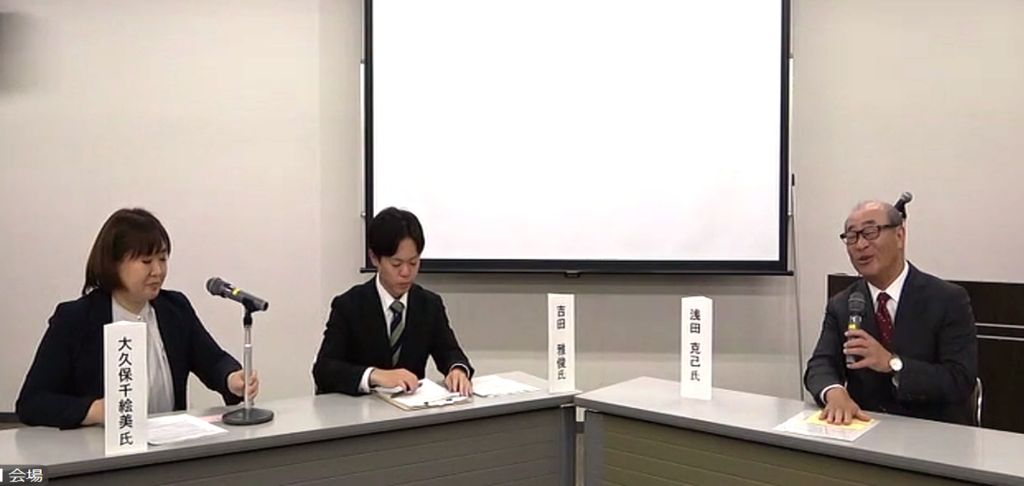第6回協同組合の地域共生フォーラムを開催しました
11月30日(土)、一般社団法人 日本協同組合連携機構(第6回協同組合の地域共生フォーラム実行委員会)は、「第6回協同組合の地域共生フォーラム」を開催しました。
このフォーラムは、医療・福祉・介護といった分野を中心に、地域に根差して事業を行う協同組合が、地域の特性にあわせ、地域のつながりを広げながら、地域完結型の「ケア」をどのように創り上げているのかを事例報告やグループ交流で学び合い、参加者それぞれの地域における活動に活かしていくことを目指し2019年から開催しています。6回目となる今回は、近年自然災害が頻発していること、阪神・淡路大震災から30年を迎えることなどから、災害時における地域での協同組合の取り組みに焦点を当て、「災害をめぐる協同組合の役割と連携のチカラ ~暮らし続けられる地域づくりのために~」をテーマに設定しました。飯田橋レインボービル(東京都新宿区)から全国に向けてオンライン配信するとともに、地域の参加者が対面で交流できるようにサテライト会場(石川県金沢市、富山県富山市、愛知県名古屋市、兵庫県西宮市)を設置し、約230名が参加しました。
ここでは、フォーラムの概要をプログラムに沿ってご紹介します。
※以下のタイトルをクリックするとご覧いただけます。
【第1部】
1.被災地からの報告(石川県)
石川県農業協同組合中央会 総務部 部長 吉田 諭氏
 今回は、災害というテーマに照らし、石川県金沢市のサテライト会場から、能登半島地震・奥能登豪雨からの復旧・復興の取り組み、被災地の状況について報告いただきました。
今回は、災害というテーマに照らし、石川県金沢市のサテライト会場から、能登半島地震・奥能登豪雨からの復旧・復興の取り組み、被災地の状況について報告いただきました。
2024年1月1日に発災した能登半島地震および津波、2024年9月21日の奥能登豪雨により、人的被害・住家被害をはじめ、能登地区JAにおいても本店・支店・その他施設に大きな被害を受けました。
JAグループ石川では、県内・県外JAグループからの物資支援、県内・県外JAグループによる募金活動、1.5次避難所(※)として開設した金沢市のいしかわ総合スポーツセンターでの避難者に対する炊き出し、JAグループ役職員による施設復旧作業等といった支援を進めてきたことが報告されました。
今後に向けては、経済産業の停滞、インフラ整備の遅れに加え、人口流出の急速化、高齢化の進展といった課題が山積する中、協同組合の強みを活かした「助け合いの精神」を全面に押し出し、必ず能登が蘇るようにさらに組織の総力を挙げた支援を継続していくと述べられました。
※1.5次避難所:ホテルや旅館といった2次避難先に入るまでの間、一時的に被災者を受け入れるため、余震などを考慮して少し離れた大型の施設に設けられた避難所。
2.イントロダクション
日本生活協同組合連合会 元会長 浅田 克己氏
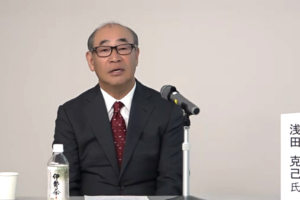 今回のフォーラムでは、日本生活協同組合連合会元会長の浅田克己氏から、過去の大震災での災害対応のご経験をふまえ、大震災において協同組合が果たした役割についてお話いただきました。
今回のフォーラムでは、日本生活協同組合連合会元会長の浅田克己氏から、過去の大震災での災害対応のご経験をふまえ、大震災において協同組合が果たした役割についてお話いただきました。
阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震において、協同組合は組織それぞれにおいて速やかに意思決定を行いながら、現地では協同組合間や行政・他組織と連携し、統一した支援の活動を実践しました。「緊急物資協定」を背景にした迅速で大量の支援物資の輸送、生協の多様な特性を活かした義捐金・見舞金、役職員・組合員のボランティア活動への参加など、協同組合の取り組みに対して、高い社会的評価がされたことも述べられました。さらには、熊本地震において組合員活動での仮設住宅訪問を行う際、生協くまもとの組合員は東日本大震災を経験したみやぎ生協の組合員にノウハウを学んだが、実はそのみやぎ生協の組合員は阪神・淡路大震災当時にコープこうべ組合員にノウハウを学んでおり、組合員間での学びや教訓の継承があったことも語られました。
また、これからの協同組合に求められる役割として、①共助の仕組みづくりへの貢献、②地域コミュニティづくりへの参加、③社会的な運動の展開の3点について、示唆がありました。
3.事例報告・質疑応答
(1)「能登半島地震における災害派遣医療チーム(DMAT)の活動報告と教訓・課題」
愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 施設課施設係長 石黒 秀典氏
 2024年1月1日に石川県で発生した令和6年能登半島地震において、DMATの一員として被災地への派遣に同行された経験から、その活動内容と活動から得た教訓や課題について報告いただきました。
2024年1月1日に石川県で発生した令和6年能登半島地震において、DMATの一員として被災地への派遣に同行された経験から、その活動内容と活動から得た教訓や課題について報告いただきました。
厚生連グループからは、延べ75隊464人がDMAT隊として現地へ派遣されていますが、初期に活動したDMAT隊の83%は厚生連病院の隊員でした。地震発生翌日の1月2日午後、厚生労働省からDMAT派遣の依頼があり、石黒氏は業務調整員として、医師1名、看護師2名、他の業務調整員2名とともに6名で愛知県の江南厚生病院からDMAT参集拠点である公立能登総合病院に向かいました。1月3日、6名の派遣先は市立輪島病院に決定し、公立能登総合病院でのミーティングの後、市立輪島病院へ向かいました。到着後はチームに分かれて、病院に残っての運営支援、転院可能な患者や外来患者の金沢市の医療機関への搬送にあたりました。1月4日は、金沢医大まで患者を搬送したのち撤収することとなり、任務を完了し、1月5日に日付が変わった頃、江南厚生病院に帰着しました。加えて、石川県の高齢者施設や1.5次避難所から愛知県内施設への高齢者受け入れにも複数回参加したこと、ロジスティックチーム(※)としての石川県庁への派遣における活動についても報告をいただきました。
これらの経験を通じて、もしもに備えて、災害等発生時の被害想定をしっかりと行っておくこと、地域特性も考慮して備蓄等の備えを行うこと、平時から関連組織との関係性構築をはかっていくことが今後の課題であると述べられました。
※ロジスティックチーム:都道府県庁や被災地域に設置される医療活動本部業務において、情報収集・分析や医療チームの指揮調整などの本部活動を行う専門のチーム
(2)「平時からの『災害支援団体のネットワークづくり』と2019年台風19号災害の取り組み」
長野県生活協同組合連合会 事務局長 中谷 隆秀氏
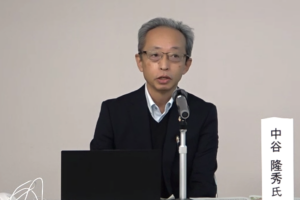 「長野県災害時支援ネットワーク」(通称「Nティアプロジェクト」を立ち上げ、災害ボランティアセンター(以下、「災害VC」)では通常実施されない農家の支援に取り組んだことが報告されました。
「長野県災害時支援ネットワーク」(通称「Nティアプロジェクト」を立ち上げ、災害ボランティアセンター(以下、「災害VC」)では通常実施されない農家の支援に取り組んだことが報告されました。
Nネットは、団体や組織の枠を超えて、平時から課題や取り組みを共有し、長野県内で災害が起きたとき、多様な団体や行政が効果的に連携し、被災者支援を円滑に行うことを目的に設置され、現在、県社協・県NPOセンター・県生協連・連合長野・県共募・JC、県長寿社会開発センター、県弁護士会(個人参加)・防災士会等の団体が参加しています。
2019年の台風19号により長野県は大規模な水害に見舞われました。中でも深刻だったのが、リンゴ農家が集まる地域の被害でした。Nネットでは、参加団体との情報共有会議を開催し、支援の連携につなぐため、被災地や被災者の困りごとや課題を共有していました。災害VCでは生活再建のお手伝いが主であり、農地の復旧や支援には関わることができません。しかしながら、大きな被害を受けたリンゴ農家は一刻も早い支援を必要としていました。そこで、災害VCとは別の枠組みで、行政の協力も得て、Nネットが事務局となり、JAや他の団体とともに「信州農業復興再生ボランティアプロジェクト」を立ち上げ、多くのボランティアを受け入れ、リンゴ農家の支援を実施しました。
この災害を経験し、分野の違う組織が平時からつながり、気軽に連絡できる信頼関係を構築しておくことの大切さを実感したこと、2025年の国際協同組合年を契機に、協同組合間はもちろん、NPOや社協、さまざまな団体とつながってネットワークを広げる必要があると述べられました。
質疑応答①(敬称略)
(浅田)石黒氏のDMATの報告では、石川県の負担を軽くするための緊急時の対応とその後の切れ目のない対応、自衛隊などとも連携した取り組みをされていたことが素晴らしいと感じた。
報告の終盤で、平時の関係性構築の重要性についてお話いただいた。専門的な知識や技能を持った方同士が平時に連携するということは、容易ではないと想定する。どのような取り組みをされているのか、お話いただきたい。
(石黒)医療の分野では、医療機関も厚生連のような公的医療機関、公立病院、大学病院、民間病院のように組織もそれぞれであり、行政機関との連携では市立病院であれば同じ市の中で一定の連携はできていると思うが、一言に連携といっても難しいと感じている。そこで今後は保健所が地域医療をいかに取りまとめていくのかがポイントになるのではないかと考えている。しかし、これにも地域での温度感に濃淡は存在しており、保健所だけで解決できない分野も多々ある。災害時の避難所や救護所の主体は市町村となり、そこに医師や看護師を派遣することになれば、医師会や看護師会との連携も必要となる。
今進めている取り組みとしては、能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報の発表をふまえて、行政の防災・福祉の担当者、消防、医師会とともに、もし南海トラフ地震が発生した時の備えが十分なのかについての話し合いをはじめている。また、この間のDMATの活動の経験などから、協同組合間連携により果たせる役割も大きいと感じている。文化連さんでは医療資器材の備蓄の準備もされていると思うので、現地派遣の中で、そして平時においてもより連携を進めていきたい。
(浅田)内向きにならずに、外向きに連携を進められている。いかに協同組合の外の組織との連携が図れるかは協同組合全体の課題であり、今後の取り組みにも期待をさせていただきたい。
続いて、中谷氏の報告では、中間支援機能を持ったNネットでの情報共有の取り組みがとても興味深いと感じた。Nネットには社協も参加しているが、運営のポイントや平時の活動についてお話いただきたい。
(中谷)長野県生協連では災害支援を行っている団体との交流が全くなかったため、災害支援団体とともに交流会を開催できないかということで、2017年に県社協、県NPOセンターに声をかけたことがNネット設立のきっかけだった。全国では災害中間支援組織が23あるが、他県でもなかなか連携が進んでいないと聞いていたため、組織の形だけつくるのではなく、日常的な情報交換や学びなど定期的に話し合う機会を設け、平時のつながりづくりを進めていくこととした。そんな矢先に台風が発生した。発災直後は身動きが取れなかったが、被災地でNネットのメンバーと顔を合わせ、情報を共有したり、困ったことを相談したりしていくことで、必要なところに必要な支援を届けることができるようになった。県内外から200近い団体がボランティアに駆けつけてくれたが、定期的に情報共有会議を開催することでスムーズな受け入れをすることができたと考えている。
その後も、平時からのつながりをつくる機会として、年に1回「災害時の連携を考える長野フォーラム」を開催しており、連携のレベルを落とさないための活動となっている。
(4)「住民の力と地域とのつながりを大切にした、被災地での仕事づくり・まちづくり」
労協センター事業団 亘理事業所「ともにはま道」所長 大久保 千絵美氏
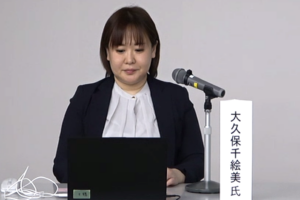 東日本大震災で仕事を失った町民5名で緊急雇用創出事業を受託し事業をスタートさせたものの、存続の危機を迎えたこと、そこから障害者就労支援施設を立ち上げ、社会福祉協議会とともにフードドライブ活動などを展開してきたことについて、報告いただきました。
東日本大震災で仕事を失った町民5名で緊急雇用創出事業を受託し事業をスタートさせたものの、存続の危機を迎えたこと、そこから障害者就労支援施設を立ち上げ、社会福祉協議会とともにフードドライブ活動などを展開してきたことについて、報告いただきました。
2012年11月、労協センター事業団は町の緊急雇用創出事業を受託し、2013年3月に「ともにはま道」の前身となる亘理事業所「産直 はま道」が開所しました。「産直 はま道」では、直売所、お弁当やお惣菜を製造販売する厨房、農業といった事業を展開しました。2014年6月、緊急雇用創出事業が打ち切りとなり事業所は経営難に陥りましたが、「単なる仕事おこしではなく、震災で亡くなった方の思いをくみ、意義や価値を注ぎ込みながら存続に向けて挑戦すること」などをはじめとした行動指針を決めて取り組みを進め、その危機を乗り越えました。そして、2016年2月に、店舗を移動して多機能型総合福祉施設を設立し、屋号を「ともにはま道」として再スタートをきりました。
「ともにはま道」では、コロナ禍にこれまでの社会連帯活動の制限を余儀なくされたことから、亘理町の社会福祉協議会と協働してのフードドライブ活動もはじめました。町内外の企業の協力を得て数ヶ所にフードボックスを設置し、ボックスに集まった食品をフードバンクに運ぶ活動に障がいのある仲間たちと取り組んでいます。
亘理町では、障がい者の支援における課題があり、安心して暮らせる地域をつくるために、さらに多くの人や機関を巻き込んだ取り組みを展開していきたいと、今後の展望についてもお話いただきました。
(5)「震災復興と市町村との包括連携協定による持続可能な地域づくり」
ふくしま未来農業協同組合 営農経済企画課 営農経済企画係兼復興対策担当 吉田 雅俊氏
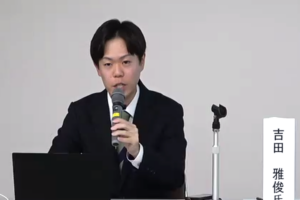 東日本大震災からの復旧・復興に向けて、JAとして取り組んできたこと、市町村との包括連携協定の締結の取り組み、協同組合間連携での取り組みについて報告いただきました。
東日本大震災からの復旧・復興に向けて、JAとして取り組んできたこと、市町村との包括連携協定の締結の取り組み、協同組合間連携での取り組みについて報告いただきました。
被災直後の取り組みとしては、被災者への炊き出しを組合員と一緒に実施しました。また、営農再開に向けた活動としては、除染・除塩作業や放射性物質検査を実施してきました。
当JAでは今年度から、東日本大震災からの復旧・復興を進め、地域経済の発展・持続性向上を実現するとともに、安全安心に暮らせる地域共生社会を創出することを目的に、管内12市町村との「包括連携協定」の締結を進めています。協定内容は「農業振興に関すること」「食農・食育に関すること」「地域・暮らしの安全・安心に関すること」「健康増進に関すること」「イベントの共催・協賛に関すること」「持続可能な農業と地域共生社会の実現に関すること」「東日本大震災からの復興と風評被害払拭に関すること」の7つです。食農・食育では、小学生や中学生を対象とした農業体験を実施したり、地域や暮らしの安全を守る活動では、従来から市町村と連携し、地域を歩く活動の多いJA職員が見守り活動などを行ったりしています。
協同組合間連携では、県外JAと包括連携協定を締結し、産地研修や生産技術・品質の向上などに取り組んでいます。また、生協との友好協力協定も締結し、農産物交流、災害時相互協力などを実施しています。
最後に、東日本大震災で多くの支援をいただいたご恩を忘れず、災害発生時には、各JA、協同組合、地域の方を支援すると同時に、平時からの連携を大事にしていきたいと述べられました。
(6)質疑応答②(敬称略)
(浅田)大久保氏からの報告の最後では、労働者協同組合法の施行から2年が経過し、2024年11月1日の時点で、全国に113の労働者協同組合が設立されていることにも触れられていた。いよいよこれからであり、労働者協同組合の動向に今後も注目していきたい。
フードドライブでは社協と連携しながら、取り組みを展開しているとのことだった。今後の取り組みに向けての展望があればお聞かせいただきたい。
(大久保)今の活動は、地域の方や企業からフードボックスに寄贈された食品を社協のフードバンクに運ぶだけだが、私たちは厨房業務も行っているので、今後は寄贈された食品を温かいお弁当などに加工して配布できないかということを話し合っている。寄贈されるのはレトルト食品が多いが、手作りの温かい食事をとっていただきたいという思いがあり、ぜひ実現できればと考えている。
(浅田)フードバンクだけでなく、労協連が加わることで、利用者への新しい価値づけや働く側にとっても仕事の価値づけができるのではないかと感じた。今後の発展が楽しみである。
吉田氏からの報告では、東日本大震災からの復旧・復興の取り組みは今もなお続いているということであった。市町村との包括連携協定の協定内容は、広範な分野に及ぶものであると考えている。それぞれに組織改編や人事異動がある中で、どのように安定的な維持をはかっていくのか、今後工夫していきたいことなどがあればお話しいただきたい。
(吉田)今年度から市町村との包括連携協定の締結を順次進めているが、締結にあたっての市町村との打ち合わせの中では「締結がゴールではなく、その後の取り組みが大事」ということを共有している。担当者が変わることで認識のずれなどが発生しないように、取り組みについて振り返る定期的な会議の設定や、担当者間ではなく担当する部署間での情報共有を図りながら進めていくこととしている。
(浅田)報告の中で、トップセールスの話もあったが、日本生協連時代、JAの会長が福島から渋谷にトップセールスに来ていただいた。この時は、対面での連携が主であったが、吉田氏のような世代では、LINEなどSNSを活用した日々のやり取りなども進んでいるのか。
(吉田)SNSでのやりとりはまだしていないが、対面だけでなくオンラインを取り入れた打ち合わせや担当者間の1対1ではなく、関連するメンバー全員が情報を共有・把握できるようにしている。
(浅田)大久保氏の報告では、動画での事業紹介もされていた。映像でのコミュニケーションや対面によらない打ち合わせなど、コミュニケーションの方法や連携の図り方についてもモダナイズ化していく必要があると感じた。
4.第1部の取りまとめ
日本協同組合連携機構 代表理事専務 比嘉 政浩
 4団体からの事例報告等を踏まえ、フォーラムで印象に残ったこと、地域で新たに取り組みたいと感じたこと、県域や地域の場で情報交換の場をつくる可能性、の3点についてグループ交流を行いました。
4団体からの事例報告等を踏まえ、フォーラムで印象に残ったこと、地域で新たに取り組みたいと感じたこと、県域や地域の場で情報交換の場をつくる可能性、の3点についてグループ交流を行いました。
グループで話し合ったことについて、三重県・愛知県のグループから「どういう手法で地域の方と健康づくりやまちづくりを進めているのか情報共有できた」、東京都のグループから「『対等性』といいキーワードが上がった。協同組合の運営側が組合員と対等性を保ちながら活動していかなければならないと改めて認識した」、そして今回初めて設置した茨城のサテライト会場から「4つの事例を聞きながら、協同労働が地域住民を主体にしていること等を認識できた。出前授業をしている協同組合があることも知った。当県の連携組織を通じて、連携の取り組みをさらに進めていきたい」といった発表をいただきました。
【第2部】
5.グループ交流・発表
第1部を終えて、印象に残ったこと、持ち帰って自分の地域で明日から取り組んでみたいこと、自組織や連携組織で取り入れられること・取り組んでみたいこと、の3点についてグループ交流を行いました。
発表ではオンラインの2グループからは、「普段からの連携は難しいが、できることからはじめて継続することが大事」、「町内の方と顔の見える関係になっていきたい」、「地域に根差して働く方も多く、仕事と関連した減災や防災を考えていく必要がある」、愛知のサテライト会場からは、「普段から各組織の強みを知っておくための活動が必要」、「2025あいち協同組合フェアを開催する」との表明もあり、兵庫のサテライト会場からは「包括連携協定の締結といったしくみもできつつあるが、そのしくみの実効性はあるのか、具体的にどのように動くのかといったことを定期的に見直す必要がある」といった発表をいただきました。
6.閉会挨拶
日本文化厚生農業協同組合連合会 総務企画部 情報教育課 課長 西出 健史氏
 本フォーラムの実行委員メンバーである日本文化厚生連の西出課長より閉会の挨拶を行いました。
本フォーラムの実行委員メンバーである日本文化厚生連の西出課長より閉会の挨拶を行いました。
本フォーラムの開催にあたっては、実行委員会の中に設置された企画チームにも参画をし、企画の検討を進めてきた。自然災害が頻発している中で、災害時には協同組合が様々なカタチで被災者・被災地に寄り添った取り組みを進めていることを再確認する機会として、今回は災害をテーマとすることとした。企画段階では、本日ご報告の事例以外にも、平時、災害発生時、復旧・復興といったそれぞれのフェーズにおける、さまざまな協同組合間連携の事例が挙げられた。これらは、協同組合が地域共生社会に積極的に関わってきたからこそ発揮されたものであると考えている。
医療・福祉・介護の分野では、地域包括ケア、地域連携が国の政策としていよいよ本格化するなか、2040年問題や人口減少による地域存続の課題も待ったなしの状況となっている。その意味では、この地域共生フォーラムがますます重要な取り組みとなってくるのではないかと感じている。
2025年は国際協同組合年であり、テーマは「協同組合がよりよい世界を築きます」である。貧困や飢餓の解消、食料安全保障の確保といった世界的な課題の解決に協同組合が果たす役割や、国内外における協同組合間連携の取り組みの促進に期待がされている。本フォーラムで学んだ災害に備えた平時からのネットワークづくりや災害時の協同組合同士の連携・たすけあいについても再確認し合える年になるものと考えている。今回の成果を次回の企画につなげていきたい。